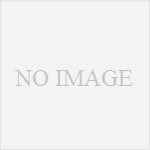概要
この日は午前のうちに外出し、宇都宮ライトレール飛山城跡駅から北へ1kmほどの場所にある飛山城史跡公園へ向かいました。
飛山城散策
この場所は名前の通り飛山城の跡で、鎌倉時代後期から安土桃山時代まで用いられた城は全体的に遺構がよく残っていて、国指定史跡として整備されています。
城域まで

手持ちの資料「関東の名城を歩く 北関東編」に掲載されているものです。
曲輪についてはこの図に従って記載していきます。
城域外~Ⅶ曲輪
Ⅵ~Ⅳ曲輪
Ⅲ~Ⅰ曲輪(主郭部)など
ここからは堀が破却されていて境が非常に分かりにくくなっています。
測量図などではⅠ、Ⅱ曲輪は非常に狭いためⅢ曲輪が主郭というイメージでしたが、現地説明板ではそうでも無い様です。
飛山城歴史
この城は鎌倉時代後期の永仁年間に宇都宮氏家臣芳賀高俊によって築かれたとされています。
芳賀氏は元々公家である広澄流清原氏の末裔だった様ですが、高俊の子である高直が主君宇都宮景綱の子を養子に受け入れ高久として当主にした事から宇都宮一門と言えます。
鎌倉幕府滅亡後、宇都宮氏は北朝方に付きますが、1339年には常陸国の南朝軍に敗れ、さらに1341年には南朝方の北畠一門である春日顕国によって落城したりします。
その上1363年、宇都宮氏綱は室町幕府内での鎌倉公方足利基氏家臣、関東管領上杉憲顕と越後守護職を争うこととなり、高久の子である高名は武蔵苦林野、岩殿山合戦で基氏らの軍勢と戦うものの大敗し、高名の子で城主だった高家が討たれるなど恵まれない時期が続きます。また氏綱の兄で高名の養子となっていた高貞が真岡城を築いたと云われている様です。以降も城は芳賀氏によって用いられますが、居城は真岡城に移っていたと思われます。
また城主だった高家の子である高清は下野勝山城へ移されています。
その後宇都宮家中では宇都宮錯乱と呼ばれる、宇都宮氏と真岡城主芳賀氏の内紛が勃発しますが、宇都宮成綱が芳賀氏を降した模様です。
しかし成綱以降、結局芳賀氏や壬生氏など重臣の専横が続き宇都宮氏は弱体化し、それを突くかの様に宇都宮錯乱で討たれた芳賀高勝の子、高照と結んだ那須氏が侵攻します。1549年に勃発した早乙女坂の戦いで宇都宮氏当主尚綱が討たれると混乱に乗じて壬生綱房が宇都宮城を占拠し、高照を傀儡の宇都宮城主とします。
その一方で高経の養子である真岡城主高定は尚綱の子広綱を滞在させます。高定は広綱を宇都宮城へ復帰させるため、外交で後北条、古河公方らの支持を得たり、高照を謀殺したりしています。
1557年、高定率いる広綱方が宇都宮城を奪還するに当たり、古河公方足利義氏の命を受けた佐竹義昭の軍勢が飛山城に在城したそうです。
その後も真岡城を居城とする芳賀氏の拠点として用いられて、高照の弟で高定の跡と継いだ高継が居を置いた事もある様です。
1597年、宇都宮氏が豊臣秀吉によって突如改易されたため、飛山城も廃城、破却された様です。またこの改易は高継の養子である真岡城主芳賀高武が原因の一つとされている様です。
感想
宇都宮ライトレール開業によって訪れやすくなったため、早速訪れた城です。
その混雑した車両内が鬼怒川を渡る際に、その河岸段丘上に築かれた様子を伺う事が出来ます。
そして城域も結構な規模で、本来なら入り口から橋を渡るべき所でしたが櫓台に釣られて外側を回ったりした事もあって結構な時間を要しましたが、それだけ見応えはあったと言えます。
またこの城の来歴は前述の通り、終始宇都宮氏重臣である芳賀氏の城であったとされてます。
ただ現在の形になったのは多分芳賀高継の時期かと思われます。
参考
現地説明板
飛山城跡公園パンフレット
関東の名城を歩く 北関東編